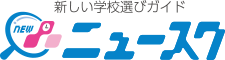通信制高校・高等専修学校ニュース

子どもが不登校になったら
原則③「前向きな姿勢を保つ」
※前記事:子どもが不登校になったら_原則②「コミュニケーションを保つ」
子どもが不登校になったら、もう対処のしようがないのか――そんなことはありません。今すぐではなくても、親子ともども少しでも良い方向へ歩み出すために、不登校の期間にできることがあります。
本サイトでは、中学生・高校生の不登校やひきこもりに関する講演録を掲載してきました。そのなかには専門家によるアドバイスもいろいろとあります。
それらのうち、すぐにも取り組めて、問題の解決に近づく方法を3つのアドバイスにまとめてみました。「ふつうの生活リズムを保つ」「コミュニケーションを保つ」「前向きな姿勢を保つ」という不登校期間の過ごし方の原則です。
シリーズ最後、3つ目の原則は「前向きな姿勢を保つ」です。
親は自分を責めないで
前向きな姿勢とは、どういうことか。
ひとつは、親が過去にこだわらないことです。
子どもが不登校になったことで「わたしの育て方が悪かったのか……」「あの時、こうしておけば……」と自分を責める保護者も少なくありません。そのような思いにとらわれるのは、ごく自然のことです。
しかし、親が過去を振り返って不登校の原因をあれこれと考えてみても、仕方のないことです。かりに原因が自分の子育てだとしても、今さらどうなるものでもありません。
それよりも、これからどうしていくかに目を向けましょう。
過去のことは変えられませんが、将来に向けての自分の態度は変えられます。不登校の子どもを変えるのは容易ではありませんが、親自身は自分の行動なら変えられます。親が変わっていく姿を見せることで、子どもの行動や意識が徐々に変わっていくと期待してみませんか。
生活リズムとコミュニケーション

では具体的にどうするか。
第1回、第2回で述べたアドバイス「ふつうの生活リズムを保つ」「コミュニケーションを保つ」を子どもと一緒に地道に続けてみることです。
「ふつうの生活リズムを保つ」と「コミュニケーションを保つ」が不登校からの脱却につながるとよいのですが、これら2つはなにも学校復帰のために提案したわけではありません。生活リズムもコミュニケーションも、いずれ子どもが自立した人間として世の中と関わっていくうえで欠かせない基本だからです。
不登校で子どもが学校生活を離れると「ふつうの生活リズムを保つ」ことも「コミュニケーションを保つ」ことも、家庭・保護者の肩にかかってきます。そう心がけて、いろいろと子どもに働きかけても、うまくいかないことも多いでしょう。
一度や二度ばかりか、三度、四度の失敗も当たり前、一歩前進二歩後退もよくあることと思い、何度でもやり直せばいいのです。叱ったり、諭したりするのに疲れたら、少し休んで、また取り組めばよいのです。うまくいかないことも「コミュニケーションを保つ」のうちです。
不登校の生徒の安心と不安

次に子どもにとって「前向きな姿勢を保つ」とはどういうことかを述べますが、その前に今回も不登校の中学生の実態をひとつ紹介します。文部科学省「不登校児童生徒の実態調査」2000年度の結果の一部です。
「学校を休んでいる間の気持ち(安心や不安)について」を尋ねたところ、中学生の答えは下の通りでした。数字は「あてはまる」「少しあてはまる」を合計した割合です。
ほっとした・楽な気持だった 69.2%
自由な時間が増えてうれしかった 66.0%
早く学校に戻りたかった 29.4%
勉強の遅れに対する不安があった 74.2%
進路・進学に対する不安があった 69.2%
自分のことが嫌で仕方なかった 58.4%
学校を休んでもいい、けれども…
この調査結果を見て、おおよそ次のように考えることができます。
不登校の当初は、学校から距離をとれたことで子どもは安心します。身体を休ませたり、心を落ち着かせたりするために、それは必要な手段だったことでしょう。特に、いじめ・いやがらせ、先生・友だちとの関係、起立性調節障害など、原因が比較的はっきりしている場合、不登校は子どもにとって緊急避難だといえます。
しかし、そのような「避難期間」が長引くと、避難そのものが問題の一端になりかねません。今回の一連の記事で再三繰り返すように、長引く不登校期間中の生活リズムの乱れやコミュニケーション力の退化が、往々にして学校復帰や進学への意欲をそぐからです。
子ども本人も、そのことに気づいてはいるのでしょう。でも、どうしていいか自分では分からなくなっていたり、分かってはいても動き出す気力がともなわなかったりしているのではないでしょうか。そのことが上の調査結果で言えば「勉強の遅れに対する不安」「進路・進学に対する不安」「自己嫌悪」に表れているように思えます。
今の学校ではなく、次の学校のことを

ここで子どもにとっての「前向きな姿勢を保つ」に話を戻します。
いま不登校の生徒、子どもにとって前向きな姿勢とは、将来へ目を向けることです。
中学校へ戻る気が起こらないのであれば、もう学校復帰のことで心をわずらわせず、高校進学の準備に取りかかってみませんか。
通信制高校を視野に入れると、進路・進学に対する不安がうんと軽くなります。不登校が長くても、そのために学力が不十分でも、通信制高校なら進学の可能性は残されます。
不登校によって不安になる一方で、「自由な時間が増えてうれしかった」というのも正直な気持ちでしょう。その自由な時間を、自分の将来についてじっくりと考えるチャンスととらえてはどうでしょう。前向きな姿勢です。
誰でも自分の将来について思いを巡らせる時が来ます。なかなか方向を決められなかったり、何度かまわり道をすることになったり、迷いを残しながら進んでみたり、様々です。すっきりと一直線に進める人は、むしろ少ないはずです。
少し先の将来のことであれ、近い将来の進学のことであれ、不登校の自分には進路選択を考える時間が他の生徒よりも早く来たと思ってはどうでしょう。これも前向きな姿勢です。
自分でする初めての大きな選択
公立校なら通う学校は、自分の住所(学区)で自動的に決まってしまいます。私立校に通う生徒では、おおかた親の意思で学校が決まった人もいるでしょう。
高校は多くの中学生にとって、はじめて自分で選ぶ学校です。せっかくの選択ですから、自分らしく学べる、自分らしく学校生活を送れる、そんな場所を少し時間をかけて見定めてみてはいかがでしょうか。
満足のいく選択のために情報を集めましょう。資料請求をしたり、進学相談会に出かけたり、また学校見学会などで高校に通う生徒の声を聞いてみたり、いまからできることはいろいろあります。
なりたい職業、就いてみたい職種に関する本を読むのもおすすめです。どんな勉強、どんな資格が必要か、それにはどんなが学校へ進むべきか、キャリアの道筋を知ることができます。ネットで調べるのもいいのですが、信頼のおける良質な情報を得ようと思ったら、時間はかかっても何冊かの本を読んでみるのが得策です。
葛藤をくぐりぬけて、新しい一歩を
最後にポイントを繰り返します。
不登校であっても、進学先の選択肢に通信制高校を含めると、中学卒業後の進路についてあまり心配しなくてもよくなります。
学校へ行かなくなってできた自由な時間がありますから、次のステップのために生かしましょう。将来のことをじっくり考えながら情報を集めて、自分に合った高校を見つけてください。
いま不登校で気分がモヤモヤしていたり、自分のことが嫌いになったりしていたら、それは苦しいかもしれないけれど、必ずしも悪くないサインです。不登校でほっとして楽な気持ちにはなったけれど、「このまま不登校でいるわけにもいかない」という気持ちもある――ふたつの気持ちがぶつかっている、葛藤の状態といえます。
少し時間がかかるかもしれませんが、「このまま不登校でいるわけにもいかない」という気持ちが優勢になると、動き出せます。といっても、それは中学校への復帰でなくてもよいでしょう。先に述べたように、高校進学へ向けて情報集めをすることでもよいと思います。
前回と前々回のアドバイス「ふつうの生活リズムを保つ」「コミュニケーションを保つ」も、どうか忘れないでいてください。
不登校であっても「ふつうの生活リズムを保つ」ことで、家族をはじめとする周囲と「コミュニケーションを保つ」ことで、苦しい葛藤を経ても、いや苦しい葛藤を経たからこそ、すっと胸の晴れるようなポジティブな方向へ歩み出せるようになると思います。