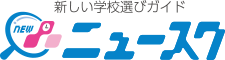通信制高校・高等専修学校ニュース

通信制高校でも大学進学は可能!希望の進路をかなえるためのポイントを解説!
不登校を経験した中高生や保護者の方のなかには、通信制高校・通信制サポート校など、全日制高校以外への進学を検討している人もいるでしょう。
しかし「通信制高校は進学に不利ではないか」「大学進学率は低いのではないか」「通信制高校に受験勉強のサポートはあるのか」などの不安を感じている人も少なくありません。
近年では、大学受験予備校や塾を母体にした通信制高校や大学進学専門コースを設ける通信制高校も増えています。
この記事では、通信制高校における最新の大学進学事情や学校の具体例などを解説します。
これから通信制高校への進学を考えていて、大学受験を目指している人はぜひ参考にしてください。
通信制高校から大学進学は可能!

通信制高校に通っていることが、大学進学に影響するケースはありません。通信制高校の特徴を正しく理解して対策を取れば、大学合格も目指せます。
今までの通信制高校は「高校卒業資格を得るための場所」という印象が強く、大学進学を目指す生徒は少数派でした。そのため、就職などの進路を選ぶ生徒や通信制高校と提携している専門学校に進学する生徒が多くいました。
しかし、近年は、通信制高校在籍者のうち大学や短大を目指す生徒の割合が増加しており、文部科学省の調査によると、通信制高校でも、20%程度の生徒が大学へ進学をしています。
なお、この20%程度という数字は公立・私立の通信制高校を合わせた割合です。そのため、私立通信制高校の大学進学率の割合は、もっと多くなると考えられます。
ここでは、通信制高校生が大学進学を目指せる理由を解説します。
- 1.大学受験予備校・塾が母体の通信制高校が増えている
- 2.大学進学を前提としたカリキュラム設計が進んでいる
- 3.個別指導やオンライン授業など学習サポートが進化している
ひとつずつ見ていきましょう。
大学受験予備校・塾が母体の通信制高校が増えている
大学受験予備校や大手学習塾が母体となる通信制高校では、大学進学を見据えた指導体制が充実しています。
たとえば、、通信制サポート校である「トライ式高等学院」は、家庭教師のトライの教育ノウハウを活かし、生徒一人ひとりに専任の教員がついて、志望校に合わせたオーダーメイドの学習プランを提供しています。自分の体調や状況に合わせてマンツーマン指導で大学進学を目指します。
その結果、2025年度大学入試において、一般的な通信制高校の約3倍である71.1%もの生徒が大学進学を叶えました。
大学受験予備校や塾が母体であれば、通信制高校でありながらも大学受験に直結する実力の養成が可能です。
大学進学を前提としたカリキュラム設計が進んでいる
大学進学コースを持つ通信制高校では、大学受験に必要な科目を重点的に学べるカリキュラムを整えています。
たとえば「第一学院高等学校」では「ウイングネット」を活用して、いつでもどこでも受験勉強ができます。
「ウイングネット」とは、市進予備校や学研の映像授業を完全個別対応で学べる映像学習システムです。教科書の理解や共通テスト対策はもちろん、英語検定対策や看護・医療系大学対策講座なども用意されています。
また「ヒューマンキャンパス高等学校」では、AI学習「atama+」を通信制高校で初めて導入しました。「atama+」とは、AIが生徒の得意不得意や目標、過去の学習内容などに応じて、一人ひとりに合った学習教材を自動作成する学習システムです。
中学校内容の学び直しや推薦対策、難関大対策など、目標に合ったカリキュラムが用意されており、2025年の大学入試の合格率は90.9%となりました。
ほかにも、通信制高校に在籍しながら全日制と同等以上の進学指導を受けられる学校が増えています。
個別指導・オンラインサポートの充実
通信制高校の大きな強みは、個別指導やオンラインサポートの充実です。
特に、「N高等学校」の「個別指導コース」では、週2回の定期面談で学習進捗の相談ができるため、無理なく学習習慣を身につけられます。総合進学クラスは、通学にもオンラインにも対応しており、自宅からでも大学受験に向けた指導が受けられます。
また、「おおぞら高校」では、オンラインを活用した学習も可能です。地域差なく国公立大学や私立文系、基礎学力完成など、目的に合わせた学習ができます。
進学校の高校生が通信制高校へ転校するメリット

進学校の高校生が通信制高校へ転校する主なメリットは以下の2点です。
- 1.時間の自由度が高まり受験勉強に集中できる
- 2.難関大学受験に必要な勉強ができる
現在全日制高校に通っている高校生の保護者のなかには「進学校から通信制に転校するのは不利ではないか」と不安を感じるかもしれません。
しかし、近年では、戦略的に通信制高校を選択し、大学進学を果たす生徒も増えています。
時間の自由度が高まり受験勉強に集中できる
通信制高校であれば、自分のペースで登校日数を調整しながら学習計画を立てられます。
大学合格に必要な学習時間は、一般的に約3,000時間といわれています。
全日制の進学校では、学校行事や長時間の授業にしばられるため、自分のペースで学習するのが難しいと考える生徒が大半でしょう。
一方、時間の自由度が高い通信制高校は、時間を有効活用し、必要な学習時間の確保がしやすくなります。芸能活動やスポーツ、アルバイトなどの趣味や自分のやりたいことと受験勉強を両立できる可能性も高くなります。
難関大学受験に必要な勉強ができる
進学校から通信制高校に転校する生徒は、難関大学受験に必要な学力の定着が可能です。
進学校の生徒は、中学時代にも高校受験勉強を経験しており、基礎学力がすでに身についています。また、高校受験での成功体験もあるため、大学受験においても高いモチベーションを維持して挑めるでしょう。
自分のペースで学べる通信制高校の学習環境を活かせれば、国公立大学や早慶上理、GMARCH、関関同立などの難関大学へ進学できる可能性もあります。
なお、GMARCHとは、以下の6つの大学を指します。
- 学習院大学(G)
- 明治大学(M)
- 青山学院大学(A)
- 立教大学(R)
- 中央大学(C)
- 法政大学(H)
実際に、「N高等学校」では、2024年度大学入試において344名もの生徒がGMARCHへ合格しました。さらに、東京大学合格者も7名輩出しています。
通信制高校から大学進学を成功させるためのポイント
通信制高校から大学進学を成功させるには、以下の3点を意識しましょう。
- 1.情報収集を積極的に行う
- 2.大学進学に強い通信制高校を選択する
- 3.模試で自分の実力を客観的に把握する
通信制高校出身であることは大学受験で不利にはなりません。大学進学をかなえるためには、戦略的かつ計画的に受験勉強に取り組み、自分に適した学習方法を選択しましょう。
情報収集を積極的に行う
大学受験は情報戦です。受験するすべての大学において、出願条件や試験科目などの情報を正確に把握する必要があります。また、各大学の出題傾向を調べ、自身に合った受験戦略を立てましょう。
さらに、大学によっては、特定の資格を保有していると有利になるケースがあります。
たとえば、「上智大学」の「学部学科試験・共通テスト併用方式」では、TOEFLや英検などの外部検定試験の結果をもとに、大学入学共通テスト外国語の点数に加点をしています。
志望大学のホームページや募集要項をよく確認し、求められる資格を取得するのもよいでしょう。
最新の大学受験情報や入試情報をていねいに伝達してくれる点も、通信制高校や通信制サポート校のメリットといえます。
大学進学に強い通信制高校を選択する
大学進学をめざすなら、受験対策やサポート体制が整っている通信制高校を選択してください。
通信制高校は自分のペースで学習ができますが、高校卒業レベルの学習を主体とする学校もあります。
通信制高校への入学や転校を検討する時に、ホームページや個別相談で進学実績を確認しておきましょう。大学受験レベルの学力が身につくカリキュラムが提供されているかも重要です。
また、通信制サポート校の利用もおすすめです。通信制サポート校では、通信制高校の学習サポートだけでなく、受験対策の指導も受けられます。
模試で自分の実力を客観的に把握する
自分の実力を客観的に把握するためには、模試を活用しましょう。模試は、自身の学習の進捗を確認し、必要な対策を立てるツールです。
通信制高校は、全日制高校に比べて生徒同士のかかわりが少なくなりがちです。そのため、自分の実力を客観的に把握したり、ほかの受験生の様子を知ったりするのが難しくなります。
「大学進学コース」を設置している通信制高校では、学校で模試の受験ができる場合もあります。また、大学受験予備校や塾に通っていなくても受験が可能です。たとえば、高校3年生の場合は以下の模試の受験がおすすめです。
| 模試 | 主催 | 特徴 |
| 全統模試 | 河合塾 | ・入試の出題方式に準拠している ・大学入学共通テスト対策以外にも、国公立大学二次試験や私立大学入試対策の記述模試など、ラインアップが充実している ・全国規模であるため、志望校までの距離を的確に把握できる |
| 駿台模試 | 駿台予備学校 | ・共通テスト系模試と一般選抜系模試の受験で、ドッキング判定による合格可能性が診断できる ・基礎学力定着から難関大学対策まで、目的に合わせて受験できる ・「駿台atama+共通テスト模試」はオンライン受験もできる |
| 東進模試 | 東進 | ・大学別模試が充実しており、中堅国公立大学や私立大学、GMARCHもカバーしている ・高校1年生・2年生対象の模試も充実している ・受験後は「東進ドットコム」で復習ツールが閲覧できる |
模試の成績表には各科目の得点はもちろん、全国偏差値や順位、志望校の合格可能性評価も記載されています。模試の結果をもとに学習計画を見直し、戦略的に受験勉強にのぞみましょう。
大学受験の選考方法
通信制高校から大学へ進学するには、大きく以下2つの入試方法があります。
- 1.一般選抜
- 2.学校推薦型選抜・総合型選抜
大学受験は学力重視の一般選抜だけではありません。自分の状況に合わせた受験方法を選択することも、合格に近づくための大きな一歩となります。
一般選抜
一般選抜とは、学力試験の得点で合否を判定する方法です。試験日が重ならなければ何校でも併願受験ができます。
国公立大学の一般選抜には、大学入学共通テストの受験が必要です。その後、2月下旬~3月上旬に二次試験を受けます。合否は、共通テストと二次試験の成績を総合的に判断して決定します。
私立大学は、2月上旬頃が一般入選抜のピークです。 私立大学の一般選抜は、大学や学部によって、受験科目や受験方法が異なります。
一般選抜では、全日制高校の生徒はもちろん、浪人生もライバルになります。高い学力が求められるため、しっかりとした受験対策が必要です。
学校推薦型選抜・総合型選抜
学校推薦型選抜には、指定校推薦と公募推薦があります。
指定校推薦とは、大学が指定した高校の生徒のみが出願できる選抜方法です。学力試験を課さない大学が多く、評定平均や書類審査などの校内選考に通過できれば高い確率で合格できます。
ただし、「早稲田大学」のような難関私立大学では、入学手続きの一環として大学入学共通テストの受験を必須としている大学もあります。また、指定校推薦でも100%合格できるとは限りません。
なお、近年では、通信制高校へ指定校推薦枠を設ける大学が増えています。現時点で希望の大学がある場合は、指定校推薦枠があるかどうかも学校選びのポイントとなるでしょう。
公募推薦とは、大学の定める出願条件と高校の学校長からの推薦の2つを満たせば、所属する高校を問わず出願できる大学入試制度です。
エントリーシートなどの書類審査や面接、小論文による選抜が一般的ですが、学力試験を課す大学もあります。
一方、総合型選抜とは、受験生の学びたい意欲や目的意識、適性、人間性などを多角的に評価する方法です。総合型選抜でも学科試験を実施する大学もあります。
公募推薦や総合型選抜では、学力だけでなく受験生を総合的に評価して合否を決めています。そのため、これまでの活動実績や特技をアピールできれば、志望校への合格も十分可能です。
委員会活動や部活動が盛んでない通信制高校の場合は、資格取得や地域のボランティアなどの課外活動に挑戦するのも良いでしょう。
通信制高校でも大学進学に挑戦できる!
通信制高校は、高校卒業資格を得るためだけの場所ではありません。近年では、大学進学に特化したカリキュラムや個別サポートを整えた学校が増えています。
現在、進学校に通っていて、人間関係や勉強に悩みを抱える高校生も目的を持って転校すれば、大学合格の可能性を高められます。通信制高校のメリットを活かして戦略的に受験勉強にのぞみましょう。
また、一般選抜や学校推薦型選抜、総合型選抜など、自身の状況に合った選抜方法を選択すれば、通信制高校でも志望校に合格できる可能性は十分にあります。
ニュースクを活用して、希望の進路が実現できる通信制高校への入学や転校を検討する際の情報収集をおこないましょう。