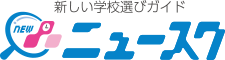通信制高校・高等専修学校ニュース

高校を辞めたい!中退するデメリットと通信制高校という選択肢
「高校を辞めたい」「学校に通うのがつらい」と悩む高校生や保護者は少なくありません。
「令和6年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要」(文部科学省)によると、高等学校における中途退学率は1.4%でした。つまり、約1,000人に14人が高校を中退しています。
しかし、高校を中退すると、学歴や進路選択などで多くのデメリットが生じます。退学を決断する前に、高校中退によって生じる影響を正確に理解しておきましょう。
この記事では、高校中退のデメリットを解説し、後悔しないための選択肢を紹介します。高校生活に悩みを抱えている方は、ぜひ参考にしてください。
高校中退のデメリット

高校中退とは、高校を卒業せずに途中で学校を辞めることです。高校中退には、主に以下のようなデメリットが生じます。
- 1.学歴が「中卒」になる
- 2.収入が大幅に減少する
- 3.将来の進学・資格取得に制限が出る
ひとつずつ解説します。
学歴が「中卒」になる
高校を中途退学した場合、最終学歴は「中学校卒業」となります。
高校を卒業しているかどうかは、就職活動や進学時に明確な影響を及ぼします。例えば、就職する際に、高卒以上を応募の条件としている企業がほとんどです。
また、高校中退者は単発アルバイトや派遣労働など、不安定な職に就く人も多いといわれています。厚生労働省の「令和5年若年者雇用実態調査」によると、15〜34歳までの労働者における正社員の割合は、大卒では87.3%である一方、高卒では63.0%、中卒では34%と報告されています。
収入が大幅に減少する
厚生労働省の統計によると、中卒の平均年収は約270万円とされています。一方、高卒者の平均年収は約300万円です。
また、長期的な生涯賃金でも、高卒と中卒では1,000万円以上の差が生じると推計されています。
参考までに、高卒で一生涯正社員として働いた場合の生涯賃金は、と大卒で一生涯正社員として働いた場合の生涯賃金差は、4,000万円以上といわれています。
もちろん、中卒でも活躍できる道はあるものの、社会人としてのスタート地点が異なる点は理解しなければいけません。
将来の進学・資格取得に制限が出る
専門学校や短大、大学に入学するには、高校卒業の学歴を有しているか、高等学校卒業程度認定試験(高卒認定試験:旧大検)に合格する必要があります。
高等学校卒業程度認定試験とは、高校を卒業できなかった人が、高校卒業と同等の学力を有することを証明するための試験です。
ただし、高卒認定はあくまで学力証明であり、高校卒業資格ではありません。そのため、高卒認定を取得しても大学に進学しなかった場合の最終学歴は、中卒となります。
さらに、看護師や保育士、公務員採用試験などの国家資格や職業資格の受験条件は「高卒以上」です。
学歴不問や、規定の年数以上の実務経験があれば取得できる資格もあるものの、中卒ではそもそも企業に採用されずに、実務経験が積めないケースもあります。
高校を中退したいと考える理由

「令和6年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要」(文部科学省)では、進路変更による退学が41.5%と最も多くなっています。
高校中退を選択する理由はさまざまですが、主な理由は以下の通りです。
- 1.進路変更
- 2.学業不振
- 3.学校生活や学業への不適応
- 4.精神的なストレスや将来への不安
それぞれ詳しく解説します。
進路変更
厚生労働省の調査で最も多く報告されているのが、進路変更による中退です。例えば、別の高校への入学や就職などです。その背景には「入学した高校になじめない」などの事情があります、
一方で、芸能活動やスポーツに専念したり海外留学したりするなど、新しい目標や夢に向かおうとするポジティブなケースもあります。
ポジティブな理由での中退も、将来の見通しが不十分なまま退学してしまうと、再び学校を辞めたくなるかもしれません。何を学び、どんな夢を叶えたいのかを明確にしてから退学を決断しましょう。
学業不振
授業内容についていけない、または登校日数が不足し進級が難しいことから中退を検討する事例もあります。
中学校までの義務教育とは異なり、高校では専門性の高い高度な学習が行われます。さらに、周囲との競争によってプレッシャーを強く感じることもあるでしょう。
また、不登校になってしまったために単位が取れず、進級が難しくなった結果、中退を選ぶ人もいます。
なお、学業の不振や宿題の未提出が重なったために学校に行きづらくなり、不登校になるケースも少なくありません。
学校生活や学業への不適応
学校生活や学業への不適応とは、学校生活になじめずに、人間関係や学業、心身の不調など、さまざまな困難を抱えている状態です。
高校生の人間関係は、クラスや部活動といった学校生活だけでなく、SNS上にも広がっています。
特に、全日制高校は、毎日の登校が必須です。日々のストレスをコントロールできず、高校中退を選択してしまう人もいます。
また、第一希望の高校へ進学できなかった場合には、高校生活に熱意が感じられないために、学習への意欲が低下するケースもあります。
精神的なストレスや将来への不安
精神的なストレスや将来への不安を感じたために、中退を選ぶ人も少なくありません。
思春期である高校生は心身ともに不安定になりやすいため、無気力状態が続くことがあります。無気力状態が続くと、心身のバランスを崩してしまい、学校へ行けなくなるケースも少なくありません。
本人にも明確な理由が分かず、誰にも相談できないまま学校から足が遠のいてしまうと、適切な支援につなげられずに中退を選択してしまう人もいます。
中退を決断する前に|通信制高校という選択肢
高校中退を検討している人にとって、通信制高校は有効な選択肢のひとつです。
通信制高校は、学び方や登校頻度を自由に選べるため、自分の状況に合わせて柔軟な学習ができます。ここでは、通信制高校の仕組みとメリット、転入学の手続きの流れを具体的に説明します。
通信制高校の仕組みと通い方
通信制高校とは、通信教育を主体とした教育課程です。添削指導や面接指導、試験を受け、高校卒業資格の取得を目指します。
通信制高校では、通学型やオンライン型など、学校によってさまざまな学習スタイルを提供しており、自分のペースや体調に合わせた学習が可能です。高校で不登校を経験した人や、毎日の通学に不安を感じる人でも安心した高校生活を送れます。
通信制高校に転入学するメリット
通信制高校に転入学する最大のメリットは、高校卒業資格を得て、大学や専門学校への進学、就職の選択肢を広げられる点です。
心身の状況や生活環境に合わせて学習できるため、現在の高校になじめなかった人でも、学習の継続が可能です。また、卒業後の進学や就職においても「高卒」として扱われます。
さらに、近年では、専門コースや職業訓練を併設する通信制高校も増えており、芸能活動やスポーツなどの新しい進路も目指せます。
高卒認定との違いを踏まえた通信制高校の強み
高卒認定は、高校卒業と同等の学力があると認められる資格ではあるものの、高等学校を卒業した事実を示す「学歴」ではありません。
一方、通信制高校を卒業すれば、全日制高校と同様の「高校卒業資格」が得られます。高卒資格を取得するためには以下の要件を満たさなければいけません。
- 3年間以上の在籍
- 74単位以上の習得
なお、現在在籍している高校での在籍期間や取得済みの単位数は、通信制高校に転学しても引き継がれるケースもあります。詳細は、転入学を検討する通信制高校に確認しましょう。
年度内転入学は12月~1月までが目安
通信制高校には、年度内の転入学の受け付けを12月〜1月頃までとしている学校があります。年度途中での転入学は、修得可能な単位数が限られる可能性があるためです。
例えば、2月以降の転入学では、ほとんどの授業をその年度内に受けられません。そのため、翌年度での履修が増えることになり、卒業時期がずれるリスクが高まります。
ただし、全ての通信制高校で12月〜1月までと期限を設けているわけではありません。学校によっては「年に4回募集」や「毎月募集」「随時受付」などのケースもあります。
通信制高校へ転入学するための手順

ここでは、通信制高校への転入学の手順を説明します。
- 1.情報収集・個別面談への参加
- 2.在籍校への報告
- 3.入学願書の記入
- 4.入学試験
- 5.入学手続き・入学
なお、転入学をするためには、在籍中の高校と転入学を希望する高校の両方での手続きが必要になるため、数週間〜1ヶ月程度の期間が必要です。早めに準備を進めましょう。
情報収集・個別面談への参加
まずは、気になった通信制高校の情報を集めましょう。近年では、公式ホームページ以外にも、SNSで生徒の様子をリアルタイムで発信している学校もあります。
なお、多くの通信制高校から気になる学校がしぼりきれない場合は「ニュースク」を活用してください。「ニュースク」では、あなたのやりたいことや特色、登校スタイルなどの希望に合った学校を探せます。
気になる学校をピックアップできたら、説明会やオープンキャンパス、体験授業などのイベントに参加しましょう。個別相談会を行っている学校も多くあります。
説明会などのイベントでは、実際に通っている生徒や保護者の声を聞ける機会もあり、リアルな情報を得られます。
在籍校への報告
転入学したい通信制高校が決まったら、在籍中の高校に転入学の意思を伝え、必要書類を発行してもらいます。必要書類は主に以下の4点です。
- 転学照会書
- 在学証明書
- 成績証明書
- 単位修得証明書
転入学先の学校の募集要項を確認し、ミスのないように準備をしましょう。また、書類の発行には1週間〜2週間程度かかる場合があります。在籍校から受け取った書類は、開封せずにそのまま提出してください。
入学願書の記入
在籍校へ書類を依頼したら、入学願書の記入をしましょう。学校によっては作文などの課題を事前に提出する必要がある場合もあります。
全ての書類がそろったら、期限までに転入学を希望する通信制高校に郵送か直接訪問して提出しましょう。
なお、詳しい出願方法は学校によって異なります。説明会や募集要項で事前に確認をしておきましょう。
入学試験
通信制高校の入試は、落とすために行うものではありません。そのため、学力試験は実施せず、在籍校から取り寄せた書類による選考や面接、作文のみの学校がほとんどです。
なお、面接では、以下のような質問がされるケースが多くあります。事前に回答を準備しておくと安心です。
- 志望動機
- 将来の夢・希望進路
- 転入学を希望する理由
志望動機や希望進路などは、作文でも問われる可能性があるため、面接と作文で一貫した回答を考えましょう。
入学手続き・入学
入試日から7〜10日前後で、本人宛に合否通知や入学手続きに関する書類、学費を納入するための振込依頼書などが郵送されます。
なお、期日までに手続きをしないと入学の意志がないと判断され、入学取り消しとなる可能性もあるため注意しましょう。
教育ローンの申請などで学費納入が遅れる場合などは、必ず転入学先の高校に相談してください。
転入学でも高等学校等就学支援金制度が利用できる
就学支援金制度とは、条件を満たせば国公私立を問わず、全日制高校・定時制高校・通信制高校に通うすべての生徒が利用できる制度です。転入学先の高校でも利用できます。
ただし、転入学をする場合は、高等学校等就学支援金はいったん受給資格が消滅します。そのため、転入学先の学校で改めて受給資格認定の申請手続きをしなければいけません。転入学の時期によっては、その月の支給を受けられない場合もあるため、転入学先の学校に事前に確認をしましょう。
また、通信制高校の就学支援金の支給期間は48ヶ月(全日制高校は36ヶ月)が上限です。在学期間が延びる場合の学費は自己負担となります。
高校中退する前に通信制高校への転入学を検討しよう
この記事では、高校中退のデメリットを解説し、後悔しないための選択肢を紹介しました。
高校中退は、学歴や収入、進学・資格取得など、将来の選択肢に大きな影響を及ぼします。しかし、その一方で「学校が合わない」「通うのがつらい」と感じている気持ちも軽視できません。
もし「高校を辞めたい」と思ったときは、勢いで退学を決めるのではなく、自分のペースで学べる通信制高校への転入学を検討してみましょう。通信制高校なら、心身の状態や生活環境に合わせて柔軟に学習し、高校卒業資格を取得できます。
なお、通信制高校では、年度内の転入学を12月〜1月頃までとしている学校が多くあります。そのため、年度内に転入学するためには、早めの情報収集が大切です。
「今の学校を続けるか、別の道を選ぶか」で悩んでいる人は、まず一度立ち止まり、自分に合った学び方を検討しましょう。
「ニュースク」を活用すれば、あなたのやりたいことや特色、登校スタイルなどの希望に合った学校が見つかります。