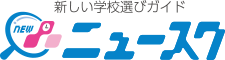通信制高校・高等専修学校ニュース

不登校のサインを見逃さないために|夏休み明けから学校に行けない子どもを支える保護者の対応を解説
夏休みが終わり、新学期がはじまり、学校から足が遠のいているお子さんもいるかもしれません。保護者の方にとっては突然の変化に戸惑い、どう向き合えばよいのか不安を感じるでしょう。
不登校には生活リズムの乱れや友人関係、勉強への悩みなど、さまざまな理由が隠れています。
この記事では、夏休み明けに増える不登校の実態と原因や、保護者ができる対応について解説します。お子さんを支えるヒントとして、参考にしてください。
夏休み明けの不登校の実態

夏休み明けはお子さんたちにとって「再スタートの時期」です。しかし、同時に不登校が増える傾向もあります。
文部科学省による令和5年度「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」では、中学生の約21.2%が9月に不登校になっています。また、9月は不登校になった時期としてもっとも多い時期です。
1学期の間に積み重なったストレスは夏休みに一度和らぎますが、夏休みが終わりに近づくと再び不安を感じ「学校へ行きたくない」と思ってしまうのです。
夏休み明けに不登校になる原因
夏休み明けに不登校になるおもな原因は以下の3点です。
- 1.生活リズムの乱れ
- 2.人間関係への不安
- 3.学業や進路への不安
ただし、不登校の原因はひとつではありません。また、複数の要因が重なっている場合もあります。原因究明にこだわりすぎずに、これからどうするのかを考えましょう。
生活リズムの乱れ
夏休み中は、自由な時間が増えるため、生活リズムが乱れがちです。朝起きる必要がないため、夜型の生活が続いてしまうお子さんも少なくありません。
数日で生活リズムを戻せれば、大きな問題にはならないでしょう。しかし、元に戻すのが難しくなっていると、登校が心身の負担となり「学校へ行きたくない」と感じてしまいます。欠席が続くとさらに学校に行きづらくなり、長期の不登校になってしまうケースもあります。
また、朝に体調が悪く登校できない場合、起立性調節障害などの身体的な病気が隠れているかもしれません。
起立性調節障害とは、小学生から成人まで幅広い年代で発症する可能性がある疾患です。
起立性調節障害のお子さんは、午前と午後で症状の強さが大きく変化します。午前中は交感神経の働きが弱く、体がなかなか活動状態に切り替わりません。そのため、めまいやふらつき、強い倦怠感を感じやすくなります。
時間が経過して午後になると副交感神経の活動が抑制され、交感神経が優位となるため、症状が軽減していきます。
夕方以降に元気になるために夜更かしが習慣化し、翌朝さらに起きられなくなる悪循環に陥るお子さんも少なくありません。
起立性調節障害は、外見からは症状がわかりにくい疾患です。そのため、保護者が「なまけている」と誤解すると、お子さんの自己肯定感を大きく傷つけてしまいます。
まずは、医療機関を受診し、医学的な検査を受けましょう。治療と生活習慣の改善を並行することで、少しずつ症状が改善するケースもあります。
友人関係への不安
学校に行けない理由として多いのが、友人関係のトラブルやいじめです。
たとえば、夏休み中に友人との関係が変化し、休み明けに再び顔を合わせるのが大きなストレスになる場合があります。また、夏休み中に人間関係に変化があるかもしれないと不安を感じるお子さんもいます。
夏休み明けに行われる体育祭や文化祭などの学校行事は、友人の有無で楽しさが変わってしまうでしょう。人間関係に不安があると、学校行事がつらいものとなるため、登校を避けようとしてしまいます。
お子さんが「学校へ行きたくない」と言った場合、無理に問いつめずに、安心できる環境を用意してあげましょう。そのうえで、担任やスクールカウンセラーに相談し、学校と連携して解決を図ってください。
学業や進路への不安が理由の場合
中学生に多いのが、学業の遅れや進路への不安から来るストレスです。
夏休み明けには、課題テストが実施される学校もあります。また、夏休みの課題が終わっていないため、教室に入りにくいと感じるお子さんもいるでしょう。
さらに、中学3年生の場合は、夏休み明けから受験勉強が本格化します。「進路について考えたくない」といった現実逃避的な思考が「学校に行かない」という選択につながる可能性もあります。
学業や進路への不安があるお子さんに対しては、学習塾や家庭教師などのような、学校以外の場で学習面のサポートをしてあげ、進路についての選択肢を広げましょう。
たとえば、通信制高校やサポート校など、自分のペースで登校できる高校へ進学ができれば、お子さんも安心して学校に通えるでしょう。
夏休み終盤や新学期に見られる不登校のサイン
不登校になる可能性があるおもなサインは以下のとおりです。
- 1.宿題をしたがらない
- 2.体調不良を訴える
- 3.外出をしたがらない
不登校は、ある日突然はじまるわけではありません。小さなサインを見逃さないことが早期の対応につながります。
宿題をしたがらない
新学期が近くなっても、宿題に手をつけようとしない場合、すでに学校に対する意欲がなくなっているかもしれません。
勉強が面倒でやらないだけではなく、宿題をしないことで学校に行けない状況を作っている可能性があります。
また、発達障害などの影響により、計画的に物事を進められない場合もあります。勉強の理解ができなかったり忘れ物をくり返したりなどの失敗体験から登校を避けようとするのです。
体調不良を訴える
新学期が近づくにつれて頭痛や腹痛などを訴えるお子さんも少なくありません。「学校へ行かなければならない」というストレスによって体調をくずしている可能性があります。特に、登校する時間に体調不良を訴える場合は、精神的な要因が影響しているでしょう。
特に、夏休み中に昼夜逆転してしまった生活リズムから規則正しい生活に戻そうとして、身体に不調が現れる場合もあります。起立性調節障害の初期症状でもあるため、医療機関への受診も検討してください。
また、活発でよく話していたお子さんが急に無口になった場合や、話しかけても反応が薄い場合なども、不登校のサインかもしれません。
「学校へ行きたくない」と言葉にして伝えられないお子さんは、体調や精神面が不安定になるお子さんもいます。
外出をしたがらない
新学期が近づくにつれて、外出を避けようとするケースもあります。
クラスメイトに会いそうな場所へ行こうとしない場合は、登校への抵抗感が高まっているかもしれません。
また、今まで興味を示していた趣味に関心を示さなくなったり、ゲームやスマートフォンへの依存度が高くなったりしている場合も注意が必要です。現実世界のストレスから逃れようとしている可能性があります。
不登校になったお子さんにできる保護者の対応

中学生や高校生が不登校になった場合、解決に向けて保護者ができる対応を紹介します。
- 1.登校を無理強いせずにお子さんが家にいることを認める
- 2.規則正しい生活を心がける
- 3.学校以外の学びの場を提供する
- 4.学校と連携する
保護者がお子さんの状況を理解し、正しく対応できれば不登校からスムーズに回復できる可能性もあります。
登校を無理強いせずにお子さんが家にいることを認める
登校を無理強いすると、お子さんをよりいっそう追いつめてしまいます。お子さんが不登校になった時は、休息が必要な時期です。学校へ行かないあせりや不安を感じても、厳しく接するのではなく、認めてあげましょう。
そして、お子さんの話に耳を傾けてください。何日か仕事を休み、一緒にゆっくり過ごすのもよいでしょう。
規則正しい生活を心がける
学校を休んでいても、お子さんの生活リズムがくずれないように気をつけてください。
家にいる時間が多くなると、ついゲームやマンガに没頭して夜ふかしをしてしまうかもしれません。しかし、昼夜逆転が常態化すると、朝起きられず学校に行けなくなってしまうでしょう。
実際に、文部科学省の「令和5年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について」でも、不登校の中学生や高校生が生活リズムの不調に関する相談をしていたケースが多くあることが報告されています。
また、昼夜逆転が続くと、家族と顔を合わせる機会も少なくなり、お子さんの安心できる場がなくなってしまいます。
規則正しい生活をするために、以下の点に気をつけましょう。
- 家族全員の夜の過ごし方を見直す
- 起床と就寝の時間を決める
- 朝の習慣を作る
- 日中は体を動かす
家族が夜ふかしをしていると、お子さんも夜型の生活になってしまいがちです。テレビやゲームなどの使用時間を決め、代わりに好きな音楽を聴くなどするとよいでしょう。家族全員が毎日一定の時間に起床や就寝をすることも重要です。
また、朝はカーテンを開けて部屋に日光を入れると、体内時計の調整がしやすくなります。日中は運動をしたり外出をしたりするのも効果的です。
学校以外の学びの場を提供する
お子さんが「学校には行きたくないけれど勉強はしたい」と思っている場合は、塾や家庭教師、フリースクールなどの利用を検討しましょう。
フリースクールとは、学校に行けなくなってしまった子どもに学びや交流の場を提供する民間の教育施設です。文部科学省が定めている要件を満たせばフリースクールへの通学を中学校の出席として認められる場合もあります。フリースクールで出席扱いが受けられれば、高校へ進学する際の内申書にプラスになるだけでなく、お子さんの自尊心も高まるでしょう。
なお、フリースクールは、学校への復帰を目標としていたり個別指導を行っていたりと、施設によって特徴はさまざまです。お子さんが前向きで明るい気持ちで過ごせるフリースクールを選びましょう。
学校と連携する
学校に行っていない期間も、担任の先生やスクールカウンセラーとお子さんの状況を共有しておきましょう。
担任の先生は、お子さんの学校での様子を良く知っています。そのため、家族が知らない情報を知っているかもしれません。進路相談なども相談できます。
スクールカウンセラーとは、学校現場において児童・生徒や保護者、教職員の心のケアをする心理の専門家です。不登校に関する知識も豊富であるため、専門的なアドバイスが得られます。教育支援センター(適応指導教室)や児童相談所などの外部機関を紹介してくれる場合もあります。
不登校になったお子さんに対して親がやってはいけない対応
お子さんが不登校になった場合、以下の行動を取るのは避けましょう。
- 1.学校へ行きたくない理由を問いただす
- 2.お子さんと距離を置く
- 3.ほかの子や兄弟姉妹と比較する
お子さんが不登校になると、保護者もあせりや不安を感じるでしょう。しかし、誤った対応をしてしまうとお子さんをもっと追いつめてしまいます。より不登校の傾向が強くなる場合もあるため、慎重に対応してください。
NG行動:学校へ行きたくない理由を問いただす
学校へ行きたくない理由を問いただすと、お子さんをさらに混乱させてしまいます。
お子さん自身にも、不登校になった明確な理由がわからなかったり言語化できなかったりする場合もあります。
また、無理に登校させようとするのも避けてください。特に、学校を休みはじめたばかりの時期は、学校への不安や恐怖心が強くなっているため、状況が悪化してしまう可能性もあります。
まずは、お子さんの気持ちを受け止めてあげて、相談したいと思ったタイミングで話を聞いてあげましょう。
NG行動:お子さんと距離を置く
お子さんと距離を置いてしまうと「自分は大切にされていない」と感じ、心を閉ざしてしまうかもしれません。
「これまで頑張ったね」「無理に学校に行かなくていいよ」と声をかけ、家族が味方であることを伝えてあげましょう。
また、どう対応すべきかわからないからといって、放置してしまうのは絶対にやめましょう。お子さんが自分から動き出すのを待つだけでなく、保護者としてできるサポートをしてください。
NG行動:ほかの子や兄弟姉妹と比較する
ほかの子や兄弟姉妹と比べるような言動は、お子さんの心を傷つけ、自己肯定感を低下させます。
悩みや感じ方は一人ひとり異なります。ほかの子と比べられ、劣等感が強くなると、回復も遅れてしまいます。お子さんの状況や個性をありのまま受け入れ、成長を見守ってあげましょう。
また、保護者自身も他人と比較してはいけません。「私の育て方が悪かったのか」などと自分を責めてしまうと、お子さんも罪悪感を感じてしまいます。
不登校の原因はさまざまあり、親の接し方や育て方が原因であるとは限りません。他人と比べずに、今の状況を受け止め、前向きに考えましょう。
中学3年生の不登校と進路の考え方
中学3年生で不登校が続くと、「高校に進学できるのか」という大きな不安が親子にのしかかります。実際、不登校だからといって高校進学が不可能になるわけではありません。通信制高校や定時制高校、さらにはサポート校を組み合わせるなど、多様な進学ルートがあります。近年では通信制高校のカリキュラムも充実しており、自宅学習をベースにしながらスクーリングやオンライン授業で無理なく学ぶことが可能です。まずは情報収集を始めることが第一歩です。「新しい学校選びフェア」のようなイベントに参加すれば、複数の学校を比較でき、進路に不安を抱える家庭にとって有益な情報源となります。お子さんにとって「自分に合った学び方がある」と知ることが、前向きに未来を考えるきっかけになります。
通信制高校という選択肢
不登校になってしまっても、高校進学は可能です。
たとえば、通信制高校は、中学校や高校で不登校になった生徒の受け入れを積極的に行っています。
通信制高校では、添削指導や面接指導、試験を受けて高校卒業資格の取得をめざします。毎日の通学が必要がない高校も多く、自分のペースでの登校が可能です。
また、サポート校と連携している高校であれば、お子さんの状況や希望にあわせて、日々の学習管理や精神的なサポートをていねいに行っています。中学校で不登校になってしまったお子さんも安心して高校生活を送れます。
さらに、通信制高校の入試では、書類選考や面接、作文のみの実施が一般的です。学科試験は簡易的に実施するか、実施しない高校がほとんどあるため、学校へ行けていない状況や学習面での不安が不利に働くことはありません。
ただし、通信制高校は年々増加しています。文部科学省の「学校基本調査 令和7年度(速報)」によると、通信制高校は全国に332校あります。膨大な数があるなかでお子さんに合った高校を選択するのは簡単ではありません。
そこで、ニュースク編集部では、進路選択に悩んでいる中学3年生に向けて「新しい学校フェア」を開催しています。
◆「新しい学校選びフェア」2025年度秋季開催日程
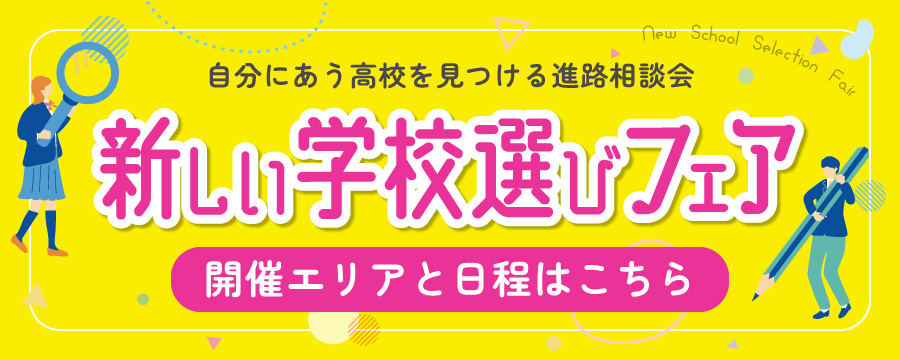
- 札幌:9月23日(火・祝)
- 仙台:9月20日(土)
- さいたま浦和:9月27日(土)
- 東京有楽町:10月4日(土)
- 横浜:10月19日(日)
- 長野:9月28日(日)
- 静岡:10月5日(日)
- 名古屋:10月25日(土)
- 岐阜:9月21日(日)
- 京都:9月28日(日)
- 大阪:10月26日(日)
- 神戸:11月8日(土)
- 岡山:11月9日(日)
- 広島:10月5日(日)
- 北九州:11月16日(日)
- 福岡:11月15日(土)
「新しい学校フェア」では、複数の通信制高校やサポート校の学校説明を一度に聞けるイベントです。どの学校の話を聞けばよいかわからない場合は、会場内のスタッフがお子さんの状況に合った学校選びをサポートします。
不登校経験のある中学生も多く参加するイベントであるため、安心してご参加いただけます。ぜひ、お子さんが自分らしい高校生活を送れる進路選択をするためのきっかけにしてください。
まとめ
この記事では、夏休み明けに増える不登校の実態と原因や、保護者ができる対応について解説しました。
お子さんが学校に行けなくなったとき、保護者としては心配や不安でいっぱいになってしまいます。
しかし、無理に理由を問いただしたり登校を迫ったりするのではなく、まずは「安心して家にいていい」と伝えることが大切です。
生活のリズムを整えたり、学校や専門機関と協力したりしながら、お子さんに寄り添って回復のきっかけを作りましょう。
また、不登校は将来を閉ざすものではありません。通信制高校やサポート校など多様な選択肢があります。
ぜひ「新しい学校フェア」へ参加をし、お子さんの次の一歩をサポートしてあげてください。