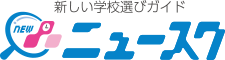子どもが不登校になった時、親ができること
[0]はじめに
[1]ふつうの生活習慣を保つこと。
[2]コミュニケーションを保つこと。
[3]前向きな姿勢を保つこと。
不登校の原因が、たとえば学校でのいじめ、あるいは精神や身体の不調のように、はっきりと突き止められる場合は、その原因を取り除くよう関係者や専門家の力を借りて解決に乗り出すことができます。
しかし、子どもに不登校の原因を聞いてみても「ただ、なんとなく……」という答えが返ってくるケースも少なくないようです。不登校の子ども本人にとっても、これといった原因があるような無いような感じで、どうして現在の状態に至ったのか漠として分からないのが正直なところだと思います。
では、不登校の原因が分からないと対処のしようがないのか――そんなことはありません。今日からすぐにでもできることがあります。
本サイトでは、中学生・高校生の不登校やひきこもりに関する講演録を掲載してきました。そのなかには専門家の講師による保護者へのアドバイスもいろいろとあります。それらのうち、すぐにも取り組めて、問題の解決に近づく方法を以下に3点挙げてみます。これら3つのアドバイスは、不登校の予防にも有効であるように思います。
[1]ふつうの生活習慣を保つこと。
起床・就寝・食事の時刻を決める、家事の手伝いなど家庭での役割を持たせる――こうして、ふつうの生活リズムを保つことが大切です。
学校に通っていれば、おのずと生活のリズムが保たれますが、不登校になると、それが難しくなります。ちゃんとできていた生活リズムも、たいてい乱れます。好きな時に起きて、好きな時に寝る。食事も自分だけ勝手な時間にとる。ゲームやスマホは、し放題……。こうした生活に慣れてしまうと、学校という規律ある環境に戻る気持ちが萎えてしまいがちですし、戻ってみても長続きしなかったりします。
すでに子どもの生活習慣が乱れているようなら、まずは起床時刻から直す、夕食は家族そろって食べるなど、ひとつひとつの習慣を定着させながら、学校へ通っている時と同じような生活リズムに近づけましょう。

[2]コミュニケーションを保つこと。
不登校の子どもは家族以外の人と話をする機会がほとんどなくなります。その家族との会話すら極端に少なくなりがちです。すると、コミュニケーション力が退化しやすくなります。家族は子どもを気遣うあまり、食事や体調などについて先回りして本人の意向を言葉にしてやるものですから、子どもはただ「うん」とか「いや」と言うだけで用事が足りてしまいます。これでは言葉で気持ちや意思を伝える力が、ますます弱ります。
日常生活での用事については周囲があまり気を回さずに、本人の方から話をさせるようにしましょう。また、家族の方も折にふれて本人の気持ちや意見をたずねるようにしたいものです。無理にたくさん話をさせる必要はありません。会話のために会話をするという不自然なことにならないようにするには、料理でも、掃除でも、買物でも、ゲームでも、何でもよいので、子どもといっしょに過ごす機会をもうけるとよいでしょう。

[3]前向きな姿勢を保つこと。
「わたしの育て方が悪かったのか……」などと親が過去を振り返って不登校の原因をせんさくしてみても、仕方のないことです。かりに原因らしきものが分かったとしても、今やどうしようもないことがほとんどです。
それよりも、これからどうしていくかが大切です。過去のことは変えられませんが、将来に向けての態度は変えられます。不登校の子どもを変えるのは容易ではないかもしれませんが、親自身は自分の行動なら変えられます。親が変わっていく姿を見せることで、子どもの行動や意識が徐々に変わっていくと期待してみませんか。
では具体的にどうするかと言えば、前項の[1][2]を弛まずに続けてみることです。短期間で解決しようと焦らず、一度や二度ばかりか、三度、四度の失敗も当たり前と思い、何度でもやり直せばいいのです。ちょっと疲れたら少し休んで、また取り組めばよいのです。
3つのポイントは以上です。
言い添えておくと、不登校を子ども本人だけの問題にせず、家族みんなで取り組みましょう。とくに[1]「ふつうの生活習慣を保つこと」では、起床や就寝、食事時間などのルールは、本人を交え、本人の理解のもと家族で取り決めます。ルールを守らせるうえで父と母の態度が違ったり、祖父母が中に入って孫の肩を持ったりなど、足並みが乱れないよう、家族みんなで一貫させることが大切です。
不登校の問題に取り組みながら、保護者もまた生活のしかた、時間の使い方を見直してみると、子どもの立ち直りに大いにプラスとなるように思います。
また、もとの学校へ復帰することだけが解決ではありません。子どもの興味や関心に沿って学校を変えてみることも選択肢に入れておきましょう。